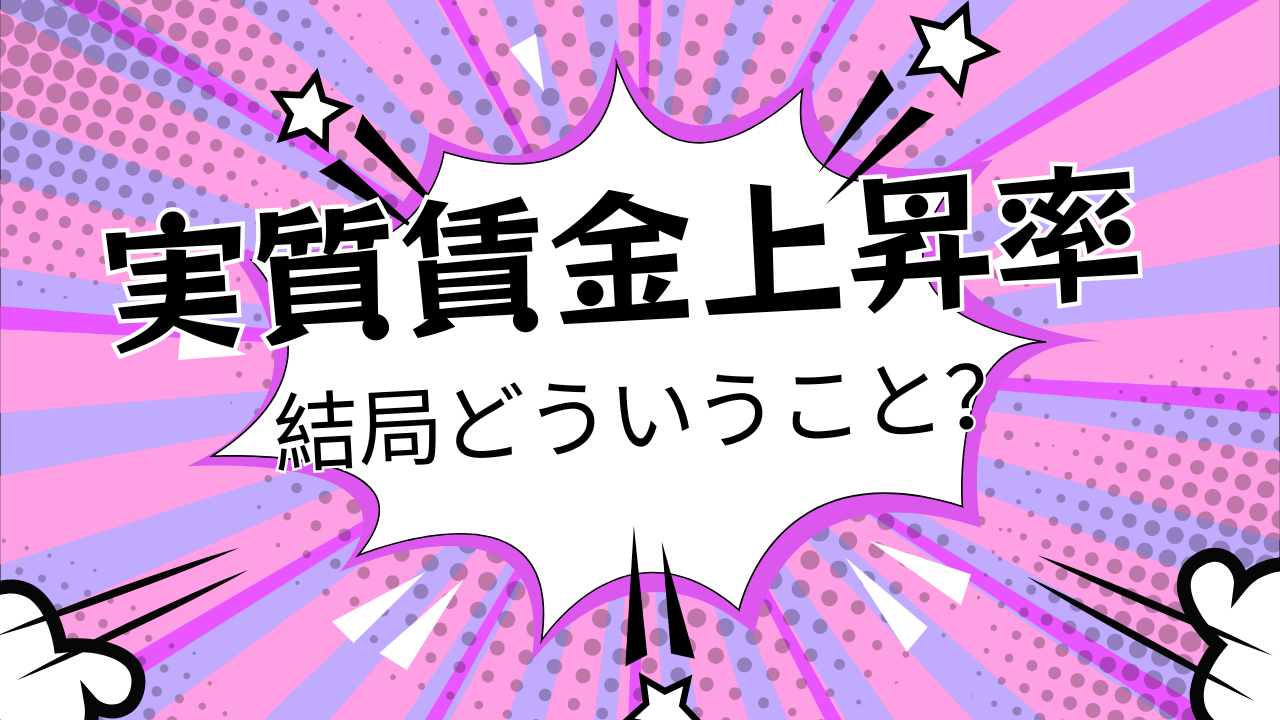
近年の日本経済は緩やかな回復基調にあるものの、中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にあります。特に、人手不足の深刻化と賃金上昇圧力は、多くの企業にとって大きな課題となっています。
コロナ禍においては、政府の資金繰り支援策や金融機関による融資姿勢の柔軟化により、倒産件数は抑制されていました。しかし、2022年以降、倒産件数は増加傾向にあり 、特に人手不足を要因とする倒産が増加しています。 2024年には、「人手不足」を要因とした企業倒産が289件に達し、2013年以降で最多となりました。
人手不足倒産の増加要因
人手不足倒産には、
- 求人難型: 思うように人材が集まらない
- 従業員退職型: 従業員の退職により人材が不足する
- 人件費高騰型: 人件費の高騰により収益が悪化する
といった類型があります。
人手不足は、人材確保のための賃上げを必要とする一方、賃上げは中小企業にとって大きな負担となり、倒産のリスクを高めます。 特に、小規模企業は資金力が脆弱なため、人手不足の影響を受けやすい傾向にあります。
賃金上昇と物価上昇の乖離
近年、賃上げの機運が高まっているものの、物価上昇率を考慮した実質賃金は減少傾向にあります。 つまり、賃金が上がっても、物価上昇によって購買力は低下し、生活はむしろ苦しくなっている可能性があります。
これは、家計だけでなく、企業にとっても大きな問題です。物価上昇は、企業の仕入れコストや人件費を増加させ、収益を圧迫するからです。
中小企業における賃上げの課題
中小企業の賃上げには、
- 業績の悪化
- 価格転嫁の難しさ
- 原材料費・エネルギー費の高騰
- 非正規雇用の増加
といった課題が存在します。
これらの課題を克服し、持続的な賃上げを実現するためには、政府による支援策の強化や、企業自身の生産性向上努力などが求められます。
政策的対応の必要性
中小企業の倒産抑制と賃金上昇促進のため、政府は、
- 助成金制度の拡充
- 税制優遇措置
- 価格転嫁の支援
など、中小企業が賃上げを行いやすい環境を整備する必要があります。
実質賃金率は、物価の上昇率を考慮した賃金の購買力を示す指標です。名目賃金が上昇しても、物価上昇率がそれを上回れば、実質賃金率は低下し、生活は苦しくなります。
実質賃金率の計算式は、以下の通りです。
実質賃金率 = 名目賃金上昇率 ÷ 消費者物価指数
社会保険料率の上昇は、直接的には実質賃金率の計算式に含まれていません。しかし、社会保険料率が上昇すると、企業の負担が増加し、賃上げの抑制や雇用削減につながる可能性があります。 その結果、労働者の手取り収入が減少し、実質賃金率の低下を招く可能性があります。
また、社会保険料率の上昇は、労働者の可処分所得を減少させます。可処分所得の減少は、消費支出の抑制につながり、経済全体の成長を阻害する可能性も懸念されます。
近年、日本においては、社会保険料率の上昇と物価上昇が同時に進行しており、実質賃金率の低下に拍車をかけています。政府は、社会保障制度の持続可能性を確保しつつ、実質賃金率の向上を図るための政策を推進していく必要がありますが、いったい今後どうなっていってしまうのでしょうか。
賃金上昇率と物価上昇率の推移
| 指標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(総合) | 102.8 | 105.6 | 102.7 |
| 名目賃金指数 | 102.8 | 104.0 | – |
| 実質賃金指数 | 100.0 | 98.5 | – |
| 中小企業の賃上げ率 | 1.96% | 3.23% | 4.45% |
注記
- 消費者物価指数は、2020年を100とした指数です。
- 名目賃金指数は、2015年を100とした指数です。
- 実質賃金指数は、2015年を100とした指数です。
- 中小企業の賃上げ率は、連合の春季労使交渉の結果に基づいています。

