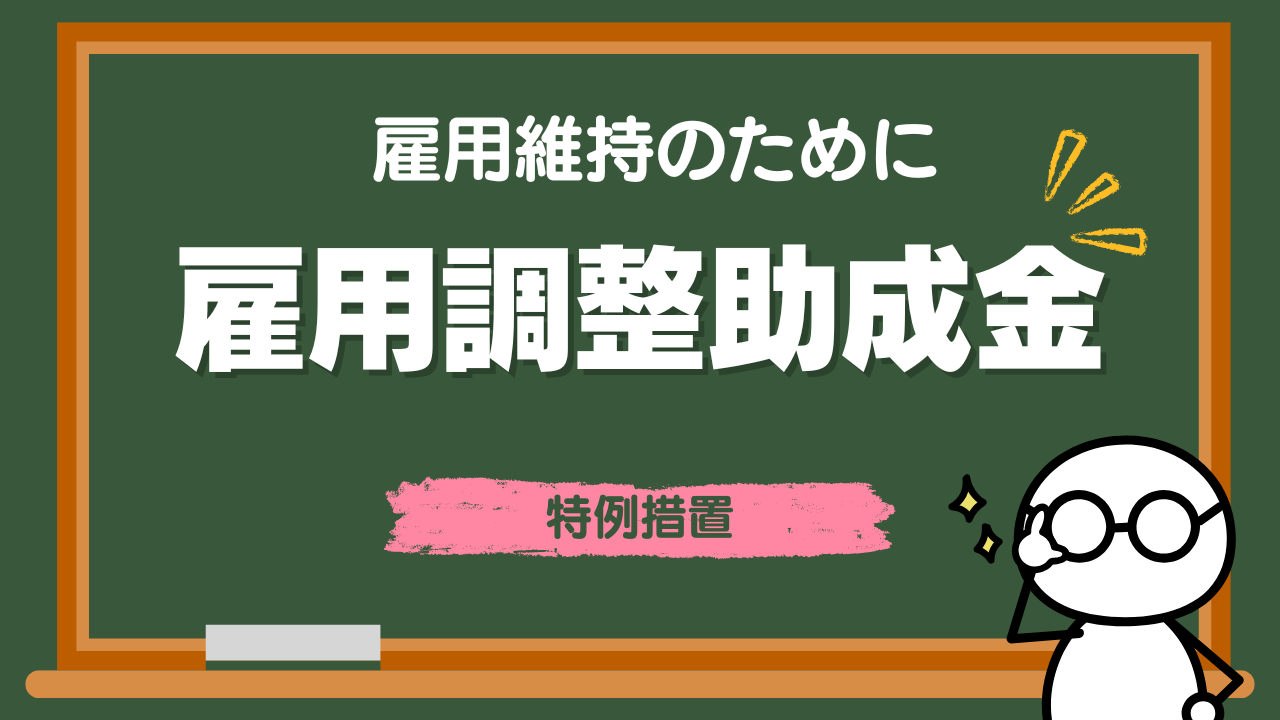
こんにちは。社会保険労務士の長谷部です。
今回は、企業の雇用維持に役立つ「雇用調整助成金」について解説します。
景気の変動や予期せぬ出来事など、企業経営を取り巻く環境は常に変化しています。そのような状況下で、企業が従業員の雇用を維持するためには、様々な対策を講じる必要があります。
雇用調整助成金は、経済的な理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業、教育訓練、出向を実施した場合に、その費用の一部を助成する制度です。
助成金を活用することで、企業は雇用を守りながら、事業の安定化を図ることができます。
本記事では、雇用調整助成金の概要から、申請のポイント、最新の特例措置まで詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持を目的として、休業、教育訓練、出向を実施した場合に、休業手当や賃金の一部を助成する制度です。1 2 厚生労働省が管轄しており、雇用保険料を財源としています。 目的は、企業の雇用維持と失業の予防です。
助成対象となる雇用調整は以下のとおりです。
- 休業
- 教育訓練
- 出向
- 在籍型出向
対象となる事業主と労働者の要件
雇用調整助成金を受給するには、事業主と労働者それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
事業主の要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高または生産量などの指標が、最近3ヶ月の月平均で前年同期より10%以上減少していること
- 雇用保険の被保険者数と派遣社員の数が、最近3ヶ月の月平均で前年同期より10%を超えかつ4人以上増加していないこと(大企業は5%超かつ6人以上)
- 過去に同助成金の支給を受けたことがある場合、直前の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(遅い方)の翌日から1年を経過していること(クーリング期間)
- 必要書類を提出するほか原本や写しを保管し、求めがあれば速やかに提出すること
- 労働局などによる実地調査が行われる場合、調査を受け入れること
労働者の要件
- 上記の事業主要件を満たす事業主に雇用されていること
- 雇用保険の被保険者であること 3
- 休業・教育訓練・出向のいずれかの雇用調整の対象となること
出向の要件
出向を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 人事交流や業務提携のためでなく、雇用調整のためであること
- 労使間の協定による、かつ出向者の同意を得たものであること
- 出向元事業主と出向先事業主との間で契約されたものであること
- 出向先企業も雇用保険の適用事業所であること
- 出向元事業主と出向先事業主が、資本・経済・組織的に無関係であること
- 出向者の受け入れに際し、出向開始前6カ月から1年を経過する日までの間に自社で会社都合の離職者を出していないこと
- 事業主が指定した1年間の対象期間内にスタートするものであること
- 3カ月以上1年以内に、出向元に復帰するものであること
- 復帰後6カ月以内に、当人を再度出向させるものでないこと
- 出向者の賃金の一部(全額でない)を、出向元事業所が負担していること
- 出向後も、出向前とほぼ同額の賃金を支払うものであること
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、雇用調整助成金の要件が一部緩和されました。
- 生産指標要件の緩和:最近1カ月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していれば、要件を満たすことになりました。
- 雇用量要件の撤廃:最近3カ月の雇用指標が増加していても、助成対象となりました。
雇用調整助成金の活用メリット
雇用調整助成金を活用することで、企業は以下のようなメリットを得られます。
- 補助金より受給しやすい: 雇用調整助成金は、他の補助金と比べて受給しやすい傾向があります。
- 返済不要: 助成金は、補助金と異なり返済する必要がありません。
- 受給金額が増額されることがある: 状況によっては、受給金額が増額される場合があります。
- 従業員満足度向上: 従業員の雇用を維持することで、従業員の満足度向上に繋がります。
助成金の支給額と支給期間
支給額
助成額は、休業、教育訓練、出向それぞれで異なります。
休業の場合
休業手当の額 × 助成率
教育訓練の場合
賃金相当額 × 助成率 + 教育訓練加算
出向の場合
出向元事業主が負担する賃金額 × 助成率
助成率は、企業規模と教育訓練の実施率によって異なります。10 3
| 企業規模 | 助成率(累計支給日数30日以内) | 助成率(累計支給日数30日超) | 教育訓練加算 |
| 中小企業 | 3分の2 | 教育訓練実施率10分の1以上:3分の2<br>教育訓練実施率10分の1未満:2分の1 | 1,200円 |
| 大企業 | 2分の1 | 教育訓練実施率10分の1以上:2分の1<br>教育訓練実施率10分の1未満:4分の1 | 1,200円 |
*表:令和6年4月以降の助成率と教育訓練加算額
1人1日あたりの助成額の上限は、雇用保険基本手当日額の最高額です。
残業や休日労働があった場合の「残業相殺」
助成対象となる休業等ののべ日数を計算する際、残業など所定外労働に該当する時間分を、休日等の日数から控除(差し引き)します。これを「残業相殺」といいます。
支給期間
休業と教育訓練の場合は、1年間で100日分、3年間で150日分が限度です。
出向の場合は、最長1年の出向期間中は支給が受けられます。
平常時と特例措置の比較
| 項目 | 平常時 | 特例措置 |
| 生産性指標 | 直近3カ月間の売上高や生産量が前年同期比で10%以上減少 | 直近1カ月間の売上高や生産量が前年同月比で5%以上減少 |
| 対象労働者 | 雇用保険の被保険者(雇用期間6カ月未満は除く)のみ | 雇用保険被保険者以外の従業員、雇用期間6カ月未満の従業員も支給対象(緊急雇用安定助成金として) |
| 助成額(率) | 休業手当の3分の2 | 休業手当の5分の4(解雇等を行わず雇用を維持した場合は10分の10) |
| 支給上限日額 | 8,370円 | 15,000円 |
| 教育訓練実施時の加算額 | 1,200円/1人1日 | 2,400円/1人1日 |
| 支給限度日数 | 1年間で100日分、3年で150日分 | 緊急対応期間中に実施した休業は、支給限度日数とは別枠で利用可能 |
申請に必要な書類と手続きの流れ
雇用調整助成金の申請は、以下の流れで行います。
- 雇用調整の計画
- 計画届の提出
- 雇用調整の実施
- 支給申請
- 助成金の受給
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
計画届提出時
- 休業等実施計画(変更)届: 雇用調整の実施計画を届け出る書類です。
- 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書: 事業活動の状況を申告する書類です。
- 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書: 雇用指標の状況を申告する書類です。
- 休業・教育訓練計画一覧表: 休業または教育訓練の計画を記載する書類です。
- 休業協定書・教育訓練協定書: 労使間で締結した協定書です。
- 事業所の状況に関する書類: 事業所の状況を証明する書類です。例:登記簿謄本
- 教育訓練の内容に関する書類: 教育訓練の内容を説明する書類です。例:カリキュラム
支給申請時
- 支給申請書(休業等): 助成金の支給を申請する書類です。
- 助成額算定書: 助成額を算定するための書類です。
- 休業・教育訓練実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書: 休業または教育訓練の実績を記載する書類です。
- 雇用調整助成金支給申請合意書: 労働者代表との合意書です。
- 支給要件確認申立書: 支給要件を満たしていることを申告する書類です。
- 労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類: 労働時間や休業日などを証明する書類です。例:タイムカード
- 教育訓練の受講実績に関する書類: 教育訓練の受講実績を証明する書類です。例:受講証明書
小規模事業主の場合
- 売上帳: 売上高を証明する書類です。
- タイムカード: 労働時間を証明する書類です。
- 給与明細: 賃金支払額を証明する書類です。
- 役員名簿: 役員がいる場合に提出する書類です。
- 通帳またはキャッシュカードのコピー: 振込先口座を証明する書類です。
小規模事業主以外の場合
- 休業協定書: 労使間で締結した協定書です。
- 売上帳: 売上高を証明する書類です。
- 事業所の規模を確認する書類: 従業員数などを証明する書類です。
- 労働・休日の実績に関する書類: 労働時間や休日などを証明する書類です。
- 休業手当・賃金の実績に関する書類: 休業手当や賃金の支払額を証明する書類です。
- 通帳またはキャッシュカードのコピー: 振込先口座を証明する書類です。
最新の特例措置
雇用調整助成金は、社会情勢の変化に応じて、特例措置が設けられることがあります。
令和6年4月からの改正
令和6年4月からは、従業員のリスキリング強化という観点から、「休業」よりも「教育訓練」による雇用維持を推進すべく、制度が改正されました。
主な変更点は以下のとおりです。
- 教育訓練の実施率が低い企業への助成率が引き下げられました。
- 教育訓練の実施率が高い企業への加算額が増額されました。
この改正により、企業は従業員のスキルアップを支援しながら、雇用を維持することができるようになりました。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年4月から特例措置が実施されました。
主な内容は、以下のとおりです。
- 助成率の引き上げ
- 支給対象者の拡大
- 申請手続きの簡素化
- クーリング期間の撤廃
これらの特例措置は、2022年11月末で終了しましたが、一部の経過措置は2023年3月31日まで延長されました。
2023年4月1日以降は、通常の雇用調整助成金制度が適用されています。
令和6年能登半島地震に関する特例措置
令和6年能登半島地震の発生に伴い、被災事業主に対して特例措置が講じられています。
主な内容は、以下のとおりです。
- 生産指標要件の緩和
- 雇用量要件の撤廃
- 計画届の提出の簡略化
- 残業相殺の撤廃(新潟県、富山県、石川県、福井県)
- 支給限度日数の拡大(3年150日を適用しない)
- 対象労働者の拡大(雇入れ後6か月未満も対象)
- クーリング要件の撤廃
- 助成率の引き上げ
申請における注意点
- 変更届の提出: 計画届の内容に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
- 休業日の自主出社: 休業日に従業員が自主的に出社した場合、助成の対象外となります。
- 申請期限: 申請期限を1日でも過ぎると、申請を受け付けてもらえません。
- 最新の情報確認: 申請前に、最新の要件や書類を確認しましょう。
- 悪質業者: 悪質業者による不正受給の勧誘には注意が必要です。
- クーリング期間: 一度雇用調整助成金の支給を受けると、その後1年間は再度支給を受けることができません。
- 申請書類の不備: 申請書類に不備や漏れがあると、助成金が支給されない場合があります。特に、中小企業では、休業手当の計算ミスやタイムカードの未整備などが起こりがちです。
よくある質問
- Q. 事業所設置後1年未満の事業主は、助成対象になりますか? A. はい、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。ただし、通常の雇用調整助成金制度では、1年以上経過している必要があります。
- Q. 労働保険の一括が行われている場合、助成額はどのように算出されますか? A. 労働保険番号ごとに助成額が算出されます。
社会保険労務士としての視点からのアドバイス
雇用調整助成金は、企業の雇用維持と事業の継続に非常に有効な制度です。
しかし、申請手続きが複雑で、要件も多岐にわたるため、自社で申請を行うのは難しい場合もあるでしょう。
そのような場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
社会保険労務士は、助成金に関する専門家であり、以下のサポートを受けることができます。
- 最新の助成金情報提供: 最新の助成金制度や特例措置に関する情報を提供します。
- 申請書類の作成・提出代行: 複雑な申請書類の作成や提出を代行します。
- 助成金受給の可能性を高めるためのアドバイス: 助成金の受給要件を満たすためのアドバイスや、申請書類の不備チェックを行います。
- 労務管理の改善提案: 助成金申請をきっかけに、就業規則の見直しや労務管理体制の改善を提案します。
- トラブルの予防: 不正受給などのトラブルを未然に防ぎます。
その他の雇用関係助成金
雇用調整助成金以外にも、様々な雇用関係助成金があります。
- 特定求職者雇用開発助成金: 高年齢者や障害者など、就職が困難な方を雇い入れた場合に助成されます。
- 仕事と家庭の両立支援: 育児休業や介護休業を取得しやすい環境を整備した場合に助成されます。
- 女性の活躍促進: 女性の採用や登用を促進した場合に助成されます。
まとめ
雇用調整助成金は、経済的な困難に直面している事業主にとって、従業員の雇用を維持するための心強い味方です。
申請を検討されている方は、ぜひ本記事で解説した内容を参考に、手続きを進めてみてください。
助成金制度は複雑で、要件を満たすための準備や書類作成に手間がかかります。
社会保険労務士は、助成金申請の専門家として、企業の皆様をサポートいたします。
助成金活用や労務管理に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
相談窓口
- 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
- 助成金レスキュー:弊所にご相談ください
免責事項
本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを構成するものではありません。
具体的な事案については、専門家にご相談ください。

